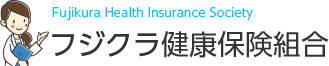病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
医療費の自己負担額が高額になるときは、マイナ保険証で受診すると、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。
マイナ保険証で受診できないときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、資格確認書とともに窓口に提出することで、支払額が高額療養費制度の限度額までになります。
マイナ保険証を提示しなかったときや限度額適用認定証の交付を受けていない場合は、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。
低所得者(住民税非課税者)
低所得者(住民税非課税者)の方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に記入し、「非課税証明書」(原本)を添付して提出してください。
「非課税証明書」(原本)はお住まいの役所で申請してください。
・療養予定期間が前年8月1日~当年7月31日の場合→前年度の非課税証明書を申請し添付
・療養予定期間が当年8月1日~翌年7月31日の場合→当年度の非課税証明書を申請し添付
8月以降も引続き利用したい場合は8月から新たに療養予定期間を指定して「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に当年度の「非課税証明書」(原本)を添付し申請してください。
- 例:令和5年8月~令和6年7月診療分→令和5年度(令和4年中収入)非課税証明書
- 例:令和6年8月~令和7年7月診療分→令和6年度(令和5年中収入)非課税証明書
- 例:令和5年11月~令和6年10月診療分→2回に分けて申請します。
- ①療養予定期間:R5年11月1日~R6年7月31日とし非課税証明書はR5年度(R4年分)を添付し申請
- ②療養予定期間:R6年8月1日~R6年10月31日とし非課税証明書はR6年度(R5年分)を添付し申請
手続き
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付